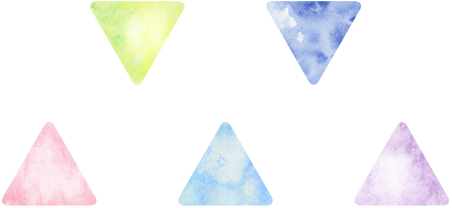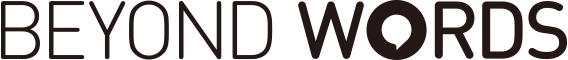こんにちは。ビヨンド・ワーズの越です。
前回のコラムの最後に、次回は、医療倫理の四原則!と書いておりましたが、ふと、「そもそも倫理って何なのか?」を書いていなかったなと思いテーマを変えました。
今回は、「そもそも倫理って?」です。
倫理は、「倫(人の輪、仲間)」と「理(模様、ことわり)」を組み合わせた言葉で、仲間の間での決まりごと・守るべき秩序のことです。社会生活を送る上で守るべき道や、善悪の判断基準と捉えると良いと思います。
では、同じような善悪の判断基準である法律とどう違うのか? 倫理は、「どのような行為が正しいか」を示します。 法律は、「どのような行為が正しくないか。やってはいけないこと」を示し、ときには罰則が明示されます。
倫理は、内から生じる自律的なもの、法律は国家から示される外的強制力のあるものです。 法は倫理の最低限(Jellinek, 1851-1911, 独)という言葉が示すように、社会におけるルールをすべて法で定めることはなく、国家権力による強制力によって守らせるべき「最低限度の規範」だけが法として定められています。
東北大学名誉教授 清水 哲郎先生が、臨床倫理プロジェクトというHPを立ち上げておられます。 その中で、倫理を「倫理は人間関係のあり方についての社会的要請」と表現されています。
私は、「倫理は人と人との関係性の中にある」というのがよく伝わる言葉で好きだなと思っています。 倫理は、「どのような行為が正しいか」を示すと書きましたが、それは、「人と人との間で、どのような行為が正しいか」を模索することだと思います。
では、クライアントとキャリアコンサルタントとの間で、どのような行為が正しいのでしょうか?
それを考える軸として、次回、ようやく医療倫理の四原則に触れようと思います。
参考サイト 臨床倫理プロジェクト
http://clinicalethics.ne.jp/cleth-prj/cleth_online/cleth_ol_top.html
前回までのコラムはこちらから読めます。